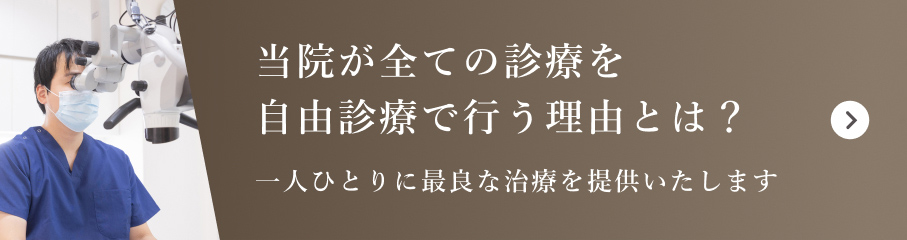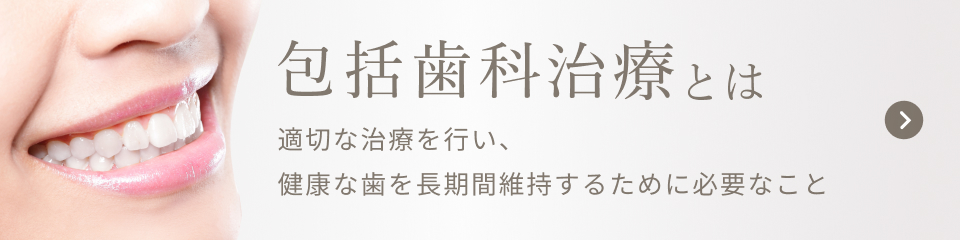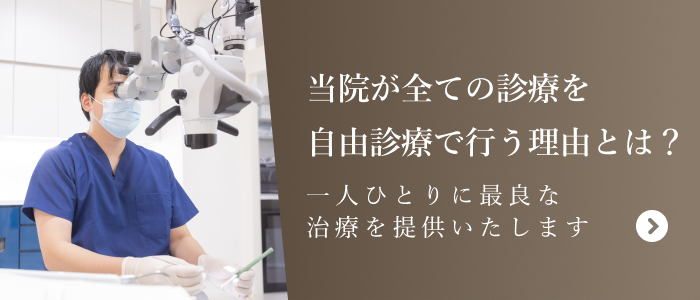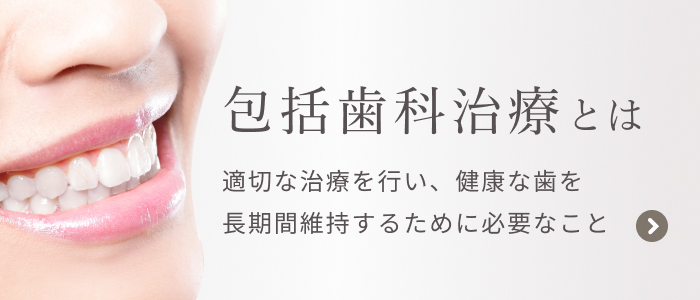神経を残す治療
歯髄とは何か―歯の中にある“生きている組織”
歯髄(しずい)という言葉を耳にしたことがある方は少ないかもしれません。
それは歯の中心部にある小さな空間の中に存在する、柔らかい組織のことを指します。
この部分には血管と神経が通っており、歯に栄養を送り、温度や痛みを感じ取る働きをしています。
つまり歯髄は、歯にとっての「心臓」や「神経系」にあたる存在なのです。
歯の表面に見えるエナメル質や象牙質は硬い組織ですが、その内部にある歯髄があるからこそ、歯は健康に保たれています。
もし歯髄を失うと、その歯は感覚を失い、栄養の供給も止まり、やがてもろく老化していきます。
神経を抜く治療―痛みを取る代わりに失うもの
虫歯が深く進むと、歯髄に細菌が侵入し、強い痛みを引き起こします。
そのときに行われるのが「根管治療(こんかんちりょう)」です。
これは、感染した歯髄を完全に除去して、内部を消毒し、詰め物をして密封する処置です。
一見すると、これで問題が解決したように思えます。
しかし、その代償は決して小さくありません。
神経を抜いた歯は、もはや自分で感じ取る力を失います。
冷たい・熱いといった感覚もなくなり、栄養の供給も止まります。
そのため歯は乾燥し、しなやかさを失い、次第にひびが入りやすくなります。
さらに、神経を抜いた歯は「再感染」に弱くなります。
根管の奥に細菌が再び侵入すると、再治療が必要になることも少なくありません。
このように、痛みを取ることはできても、歯そのものの寿命を縮めてしまう。
それが従来の「神経を抜く治療」の限界です。
歯髄保存という発想―神経を守るという選択肢
歯髄保存治療とは、虫歯が深く進行しても、感染していない歯髄を残す治療法のことです。
これまでは「虫歯が神経まで達したら抜く」という考えが主流でした。
しかし近年、歯科の研究が進むにつれて、歯髄は部分的にでも残せば再生できることがわかってきました。
つまり、すべてを取り除かなくても、健康な部分を守り、自然の修復力を活かす治療が可能になったのです。
この治療は「部分断髄法」や「直接覆髄法」と呼ばれることもあります。
いずれも、感染部分だけを慎重に取り除き、残った神経を特殊な材料で保護しながら自然に修復を促します。
技術の進歩― MTAセメントという素材の登場
歯髄保存治療が現実的になった大きな理由の一つが、MTAセメントという材料の開発です。
MTAとは、鉱物を主成分とする医療用セメントで、生体との相性が非常に良いのが特徴です。
歯髄を刺激することなく、逆に組織の再生を助ける作用があります。
また、強い封鎖性を持つため、細菌が内部に再び侵入するのを防いでくれます。
かつては「神経を残すのは危険」とされていたケースでも、MTAを用いることで安全に保存できるようになりました。
この技術の進歩によって、世界中の歯科医が「神経を残す治療」に再び光を見出したのです。
歯髄保存治療の流れ
実際に歯髄保存治療がどのように行われるのか、その一般的な流れを紹介します。
まず、診断が最も重要です。
歯髄がまだ生きているかどうか、どの程度炎症が進んでいるかをレントゲンやCTで詳しく確認します。
そのうえで、感染している部分だけを丁寧に取り除きます。
ここでは、マイクロスコープという歯科用顕微鏡が活躍します。
肉眼では見えないほど細かい部分を拡大して見ることができるため、必要最小限の削除が可能になります。
感染部を除去したあとは、残った歯髄をMTAセメントなどで覆い、密閉します。
その後、仮の詰め物をして経過を観察し、炎症が落ち着けば最終的な修復処置を行います。
治療は通常1~2回で終わりますが、術後は数か月~1年程度の経過観察が推奨されます。
歯髄保存の成功率と限界
歯髄保存治療の成功率は、おおむね70~90%といわれています。
ただし、それは適切な条件が整っている場合に限られます。
虫歯が深くても、歯髄がまだ生きており、出血がコントロールできる段階であれば成功率は高くなります。
逆に、感染が根の方まで進行している場合や、神経がすでに壊死している場合は、残念ながら保存は難しいです。
したがって、この治療で最も大切なのは「早期発見」と「早期介入」です。
痛みを我慢して放置してしまうと、神経を救うチャンスを逃してしまうのです。
歯髄を守るためにできること
歯髄保存は、虫歯が進んでからの治療法ですが、何より大切なのは「虫歯を進ませない」ことです。
そのために日常で意識したい習慣を挙げてみましょう。
一つ目は、定期的な検診です。
虫歯は初期段階では痛みがないため、自分では気づきにくいものです。
半年に一度でも歯科医院でチェックを受けることで、神経を残せるタイミングを逃さずに済みます。
二つ目は、食生活の見直し。
糖分の多い食べ物や酸性飲料の摂りすぎは、虫歯の原因になります。
甘いものを食べた後は水で口をすすぐだけでも効果があります。
三つ目は、毎日のブラッシング。
強くこするよりも、柔らかい毛で丁寧に磨くことがポイントです。
歯髄保存と再生医療の未来
歯髄を守る治療が注目される一方で、再生医療の分野でも新しい挑戦が始まっています。
それが「歯髄再生治療」です。
これは、患者自身の幹細胞を利用して、失われた歯髄を再生させる研究です。
まだ実用化の途中ですが、動物実験や一部の臨床研究ではすでに成果が報告されています。
もしこれが一般化すれば、「神経を抜いても再生できる」という未来が訪れるかもしれません。
しかし、やはり理想は“失わないこと”。
歯髄保存は、その第一歩となる大切な選択です。
まとめ―歯の命を守るという考え方
私たちは長い間、「痛くなったら削る」「悪くなったら抜く」という治療を繰り返してきました。
けれども今、歯科医療は新しい時代に入っています。
それは、「削らない」「抜かない」「生かす」という方向です。
歯髄保存とは、まさにその象徴的な治療です。
神経を残すことは、歯の感覚を守り、栄養を保ち、歯を本来の状態で長く使うための最も確実な方法です。